この度は、白石茂義公認会計士事務所のホームページをご覧いただき、誠にありがとうございます。
今回は、「長時間労働の本当の原因」について考えてみたいと思います。
この問題の本質は……
OECD国際教員指導環境調査(TALIS)2024報告書が公表されたことに伴って、2025年10月7日の新聞各紙では、働き方改革が進められているにも関わらず、日本の教員業務時間が国際的な平均時間よりも長いことが報じられていました。
そこで、今回は日本の教員業務時間に関する問題ではありますが、「もしも、これが一般的な企業にも普通に当てはまるデータなのだとしたら……」と少し解釈を広げて、この問題の本質について考えてみたいと思います。
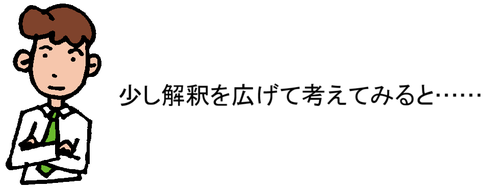
あくまでも私個人の感想ではありますが、この日本の教員業務時間が国際的な平均時間よりも長いという問題の本質は、依然として長時間労働が続いているという点よりも、「日本の常勤教員は一体誰のために働いているのか?」という目的意識が教育制度全体を通して曖昧になっている点にあるように感じました。
なぜなら、OECD国際教員指導環境調査(TALIS)2024報告書のデータを見ると、日本の常勤教員の仕事時間の合計が国際的な平均時間よりも目に見えて長いにも関わらず、その内訳である授業の時間については国際的な平均時間よりも短いからです。
つまり、これらのデータを見ていると、日本の常勤教員の仕事時間が国際的な平均時間よりも長いのは、学校運営業務や事務業務などに要する時間が非常に長いことが主な原因であるように推察され、日本の常勤教員は重要性の乏しい作業に貴重な労力を割いているのではないかという疑いを持ってしまうのです。
そうなのだとすると、まず行うべきは“必要な仕事”と“不要な仕事”の仕分けであり、その判断基準は「日本の常勤教員は一体誰のために働いているのか?」という観点から設定されるべきだと考えます。
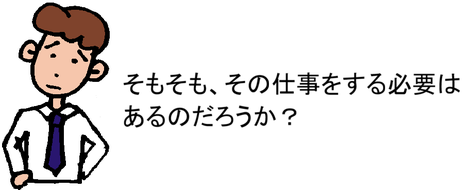
一般的な企業にも当てはめて考えてみると……
この問題を一般的な企業にも当てはめて考えてみると、長時間労働の問題を抱えている企業についても「自分たちの顧客とは誰なのか?」という点をきちんと理解しておくことが必要だということになるはずです。
ただ、先ほどの日本の常勤教員の場合とは違い、一般的な企業の従業員という括りになると、ライン業務に従事している場合には、その企業の製品やサービスを購入してくれる外部の人や組織が顧客ということになり、スタッフ業務に従事している場合には、そのサポートによる恩恵を受ける内部の人や組織ということになります。
そして、このことを十分に理解できているなら、顧客が求めているものが何であるのかを常に意識するようになるので、自分たちは顧客に何を提供しなければならないのかを把握して、自分たちが仕事として行うに値するものと、自分たちが仕事として行うに値しないものを、きちんと区別できるようになるはずです。
以上のような説明の仕方をすると、中小企業の経営者であるあなたは「そんなことをしなくても普通に区別できるはずだ!」と思われるかもしれませんが、実は、何のために行っているのか担当者にも分かっていない仕事というのは探せば意外とあります。
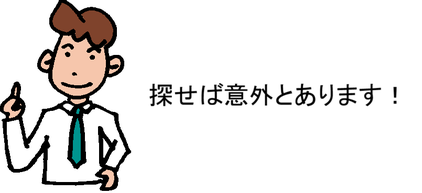
「そんな馬鹿な……」とは思わずに、まずは上述した要領で、“必要な仕事”と“不要な仕事”の仕分けを行ってみては如何でしょうか?
前へ← →次へ
白石茂義公認会計士事務所では、士業コンシェルジュというコンセプトのもと、特に、愛媛県松山市、今治市、新居浜市、西条市の経営者の皆様からのお問い合わせをお待ちしております。
必要の際には、ぜひ、お気軽にお問い合わせください。
 白石茂義公認会計士事務所
白石茂義公認会計士事務所 