この度は、白石茂義公認会計士事務所のホームページをご覧いただき、誠にありがとうございます。
今回は、「ダイバーシティ経営」について解説してみたいと思います。
ダイバーシティ経営とは何か?
中小企業の経営者であるあなたは、「ダイバーシティ経営」って聞いたことがあるでしょうか?

経済産業省のホームページを見ると、ダイバーシティ経営を「多様な人材を活かし、その能力が最大限発揮できる機会を提供することで、イノベーションを生み出し、価値創造につなげている経営」のことだと定義しています。
そして、「多様な人材」について、「性別、年齢、人種や国籍、障がいの有無、性的指向、宗教・信条、価値観などの多様性だけでなく、キャリアや経験、働き方などの多様性も含みます」とあるので、グローバル化されていない中小企業であってもダイバーシティ経営を実践することは十分に可能です。
つまり、ダイバーシティ経営とは、組織で働く人々のそれぞれの違いを尊重し、それを組織としての強みへと昇華する経営手法のことであり、広く捉えると、何かと話題になっているDEI(Diversity<多様性>、Equity<公平性>、Inclusion<包括性>)という考え方を経営の場面に適用したものだと解釈することができます。
更に、ダイバーシティ経営は人材の多様性という観点から企業価値を向上させようとする経営手法なので、前回の持続的に企業価値を向上させるためには、人的資本経営という選択は正しいと思うのですが……で説明した「人的資本経営」の一形態であると考えることもできます。
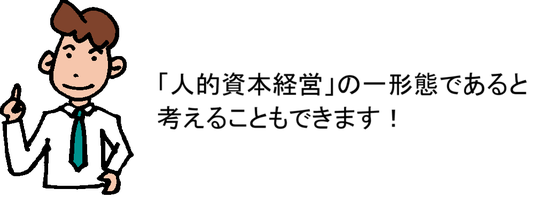
上手く機能させるためには……
このようなダイバーシティ経営ですが、あなたが気になるのは本当に効果があるのかどうかという点でしょう。
これについては、ダイバーシティ経営を採用して上手くいっている企業もあれば、上手くいっていない企業もあるようですから、この事実を素直に受け入れるならば、ダイバーシティ経営が上手く機能するには一定の条件を満たしていることが必要だと考えられます。
確かに、人材の多様性が新しい視点を現場に持ち込むことによって、イノベーションを起こしやすくすることは間違いないと思いますが、一方で、人材の多様性は従業員間のコミュニケーションを難しくしたり、チームワークを乱したりする要因にもなるので、そのままだとイノベーションを起こすどころではなくなってしまうはずです。
そうだとすると、ダイバーシティ経営を上手く機能させるためには、人材の多様性に対する従業員の耐性をつけることで、人材の多様性への許容性を高めるような対策を講じる必要があるように思います。
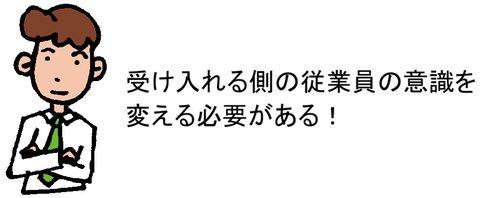
例えば、ダイバーシティ経営やDEIに関する社内研修を頻繁に行うことで、ダイバーシティ経営やDEIという考え方への従業員の理解を深めようとしたり、従業員間でのコミュニケーションを円滑にするためのツールを用意したりすることで、従業員間でのコミュニケーションに齟齬が生じないような工夫をしたりする等の対策が考えられます。
もちろん、これらの対策を実施すると共に、従業員が人材の多様性を積極的に受け入れるような組織文化(企業文化)が形成されるように仕向け、リーダーシップを発揮して従業員が人材の多様性を積極的に受け入れるように意識改革をすれば、ダイバーシティ経営が上手くいく確率は大きく上がるはずです。
そのため、ダイバーシティ経営が上手くいくかどうかは、経営者のダイバーシティ経営に対する姿勢こそがカギを握るということになるでしょう。
前へ← →次へ
白石茂義公認会計士事務所では、士業コンシェルジュというコンセプトのもと、特に、愛媛県松山市、今治市、新居浜市、西条市の経営者の皆様からのお問い合わせをお待ちしております。
必要の際には、ぜひ、お気軽にお問い合わせください。
 白石茂義公認会計士事務所
白石茂義公認会計士事務所 