この度は、白石茂義公認会計士事務所のホームページをご覧いただき、誠にありがとうございます。
今回は、「重要性の原則」について解説したいと思います。
重要性の原則とは何か?
中小企業の経営者であるあなたは、「重要性の原則」って聞いたことがあるでしょうか?
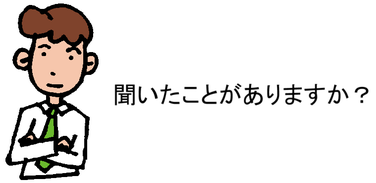
重要性の原則とは、『企業会計原則』の企業会計原則注解の注1において、「企業会計は、(中略)重要性の乏しいものについては、本来の厳密な会計処理によらないで他の簡便な方法によることも、正規の簿記の原則に従った処理として認められる。」と規定されている原則のことであり、実務に与える影響が大きいという特徴を有しています。
注目して欲しいのは、前回説明した正規の簿記の原則との関係で重要性の原則が規定されているという点であり、正規の簿記の原則の対象範囲をどう解するのかによって、企業会計原則における重要性の原則の位置付けも変わってくるという点です。
つまり、正規の簿記の原則を狭義説によって解するのであれば、重要性の原則は独立した包括原則の一つということになり、正規の簿記の原則を広義説によって解するのであれば、重要性の原則は正規の簿記の原則に含まれる関係にあるということになります。
更に、企業会計原則注解の注1は一般原則四や貸借対照表原則一の注解としても位置付けられているので、重要性の原則は明瞭性の原則や貸借対照表完全性の原則とも関係を有していると解されています。(こちらについては、また別の機会に説明したいと思います。)
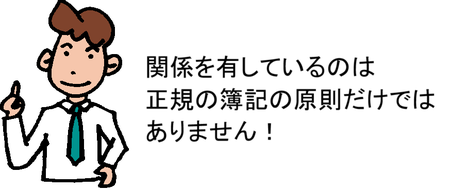
誤解している人もいるかもしれませんが……
重要性の原則に関して誤解して欲しくないのは、重要性の乏しいものについて簡便な会計処理や表示を容認しているだけでなく、重要性が高いものについては厳密な会計処理や表示を強制しているという二面性を有する原則であるという点です。
そのため、重要性が高いと考えられるケースであるにも関わらず、簡便な会計処理や表示をしていたのであれば、それは重要性の原則に反することになり、そうならないためにも、何をもって重要性が高いと判断したり、重要性が乏しいと判断したりするのかを事前に把握しておくことが非常に大切になります。
これについては、貸借対照表や損益計算書などを利用する人たちの意思決定に与える影響の大きさ(=そのような情報を知らされることで、そうでない場合とは異なった意思決定をする可能性が高いのかどうか)によって判断するべきです。
なぜなら、重要性の乏しいものについて簡便な会計処理や表示が容認されるのは、厳密な会計処理や表示をする場合に要する手間(コスト)と、そのような会計処理や表示をする場合の貸借対照表や損益計算書などを利用する人たちの意思決定に与える影響の大きさ(ベネフィット)を比較して、相当な手間を要するのに、貸借対照表や損益計算書などを利用する人たちの意思決定に与える影響が小さいのであれば、わざわざ厳密な会計処理や表示をする意味がないと考えられるからです。
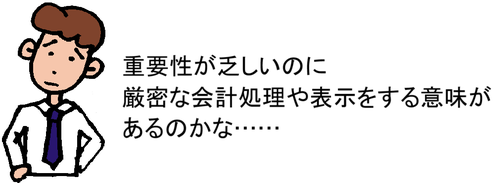
そこで、対象となる項目の金額の多寡によって重要性を判断する量的な判断基準と、対象となる項目の内容によって重要性を判断する質的な判断基準の2つの基準によって、対象となる項目に対して厳密な会計処理や表示が強制されるのか、それとも、簡便な会計処理や表示が容認されるのかを判断することになります。
次回は、「明瞭性の原則」についてお話ししたいと思います。
白石茂義公認会計士事務所では、士業コンシェルジュというコンセプトのもと、特に、愛媛県松山市、今治市、新居浜市、西条市の経営者の皆様からのお問い合わせをお待ちしております。
必要の際には、ぜひ、お気軽にお問い合わせください。
 白石茂義公認会計士事務所
白石茂義公認会計士事務所 