この度は、白石茂義公認会計士事務所のホームページをご覧いただき、誠にありがとうございます。
今回は、「銀行が貸金庫業務を止めない理由」について考えてみたいと思います。
かなり厳格な管理体制が敷かれているような印象を持っていたのだが……
中小企業の経営者であるあなたは、「銀行の貸金庫」を利用した経験はあるでしょうか?
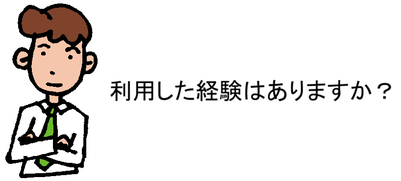
銀行の貸金庫業務については、三菱UFJ銀行の元行員が起こした窃盗事件が記憶に新しいと思いますが、メガバンクに限らず、地方銀行なども貸金庫業務を行っており、銀行が提供する業務としては珍しいものではないと思います。
ただ、恥ずかしながら私個人としては銀行の貸金庫を利用したことは一度もなく、監査法人に勤務していた時に、監査手続の一環として、監査対象であった企業の責任者の方と共に銀行の貸金庫が設置された部屋に入り、貸金庫を開けてもらって、預けている有価証券や契約書などが記録通りに実在しているのかを一緒に確かめたことが何度かあるだけです。
その時の印象では、かなり厳格な管理体制が敷かれているような感じがしたのですが、先ほどの三菱UFJ銀行の元行員が起こした窃盗事件に関する報道や、その後に報じられた過去にみずほ銀行でも似たような手口で元行員が窃盗事件を起こしていたという報道を見ると、それらの銀行では貸金庫の予備鍵の管理がずさんで、お粗末な管理体制が敷かれていたようです。
多くの銀行が今後の状況次第といった感じで様子見を決め込んでいるが……
このように元行員による窃盗事件により、意図せず世間の注目を集めてしまった銀行の貸金庫業務ですが、それ以外にも貸金庫を犯罪や脱税などに利用される危険などもあり、銀行側としては貸金庫業務を続けることはリスクが大きく、できるなら貸金庫業務を止めたいというのが本音でしょう。
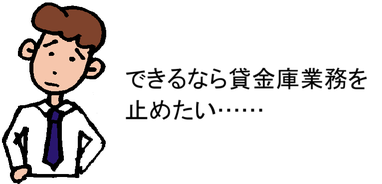
ただ、事件発覚後の報道などを見ると、一部の銀行が貸金庫業務を廃止する意向であることを公表しているものの、多くの銀行が今後の取扱いについては厳格化を進めると表明するだけで、廃止するかどうかは今後の状況次第といった感じで様子見を決め込んでいます。
その理由として考えられるのは、やはり銀行の貸金庫業務を利用しているのは富裕層が中心であり、彼らとの接点として活用できることで、他の業務(預金業務や資産運用業務など)も利用してもらい、貸金庫業務から利益は得られなくても、銀行全体として見た場合に大きな利益を得ることができるからでしょう。
更に、リアルな店舗網を持つことが難しいオンライン銀行(ネット銀行)との対比で考えれば、既に地域に密着した店舗網を持っている銀行にとっては、銀行の貸金庫業務は立派な差別化要因となるので、そのようなメリットを手放さないためにも貸金庫業務から撤退することは難しいと考えられます。
しかし、今後は窃盗に対する疑惑の目を向けられることで、銀行が貴重品を預かることへの社会的な責任が大きくなっていくことは避けられず、又、貸金庫業務に対する金融庁の監督指針も厳格化されることは間違いないでしょうから、これまでのように貸金庫に預けられた貴重品が何であるのかを銀行側は全く関知しないという状態は許されなくなるでしょう。
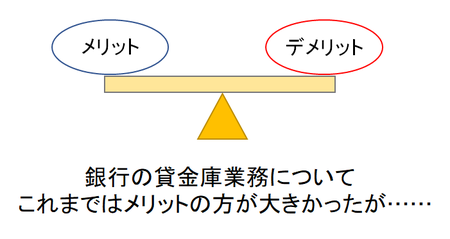
そうだとすると、銀行が貸金庫業務を続けられるのかは、そのような銀行の関与を顧客が受け入れることができるのかにかかっているように思います。
その13へ← →その15へ
白石茂義公認会計士事務所では、士業コンシェルジュというコンセプトのもと、特に、愛媛県松山市、今治市、新居浜市、西条市の経営者の皆様からのお問い合わせをお待ちしております。
必要の際には、ぜひ、お気軽にお問い合わせください。
 白石茂義公認会計士事務所
白石茂義公認会計士事務所 